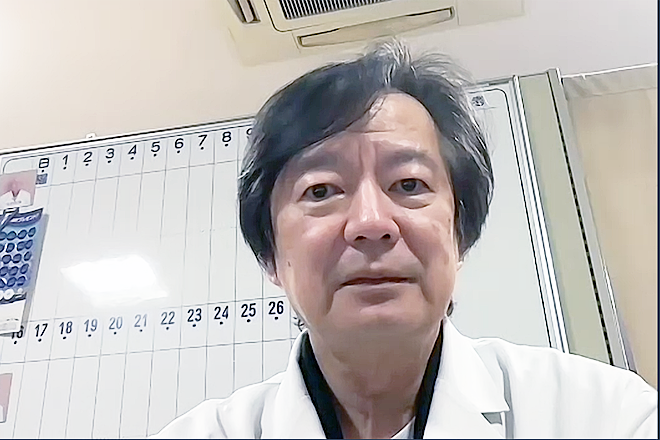
能登半島地震で被災した石川県七尾市に診療所を構える日本医師会の佐原博之常任理事は15日、本紙のオンライン取材で、震災から2週間経過した現在も、被害の大きかった半島北部では、診療所の活動が限定的だと説明した。「もともと診療所が少なく、高齢医師の診療所も多い地域だ」と述べ、医療過疎が加速化する可能性を懸念した。
佐原氏によると、14日前後の段階で、北部の診療所で限定的にでも診療を再開しているのは、輪島市が11カ所中6カ所、珠洲市が6カ所中3カ所、能登町が6カ所中5カ所、穴水町は全5カ所となっている。しかし、通常の診療ができているのは、全部で3カ所程度だという。建物の損壊などが診療再開を阻む要因となっており、「限定的な診療をしているところでは、電話のみで対応しているケースも多いようだ」と話す。
●北部へのアクセス、「極めて困難」
七尾市に設置したJMAT(日医災害医療チーム)調整支部で、佐原氏は調整に当たっているが、JMATの活動は北部まで十分に行き届いていない。
「七尾市内から日帰りできる志賀町、穴水町を中心に、避難所の医療支援などの活動を始めた。輪島市を含めて北部への支援も始めているが、アクセスが極めて困難」だとした。道路状況に加え、大雪など悪天候の影響もある。「電波が届かない地域も多く、途中で事故があった場合に、連絡が取れなくなってしまう可能性もある」と説明した。
「本来は災害時の超急性期をDMAT(災害派遣医療チーム)が担い、急性期から亜急性期をJMATが担う流れだが、能登北部では現在もDMATなどが支援を続けている状態だ」と述べた。
●避難所で深刻化する感染症
佐原氏の診療所は、建物の損壊は免れたが、駐車場に亀裂が入るなどの被害があった。現在、午前中は通常診療、午後は電話での診療を行っている。14日までは暖房がつかず、スタッフは「ダウンジャケットを着て診療に当たっていた」という。断水は今も続いており、仮設トイレを利用している。
七尾市内では、断水の影響はあるものの、多くの医療機関が限定的に診療を再開している。避難所で深刻化している感染症関連の受診も増えている。「現在、感染が判明した患者を収容する避難所の設置を、七尾市と相談している」とした。
医療関係者の被災地支援に、謝意も示した。「DMAT、JMATなどで日本各地から応援に来ていただいている。被災地住民として、被災地で医療を行う者として、感謝したい。発生直後から調整に当たっていただいている日医、石川県医師会、全国の都道府県医師会の皆さまにも感謝したい」と語った。








