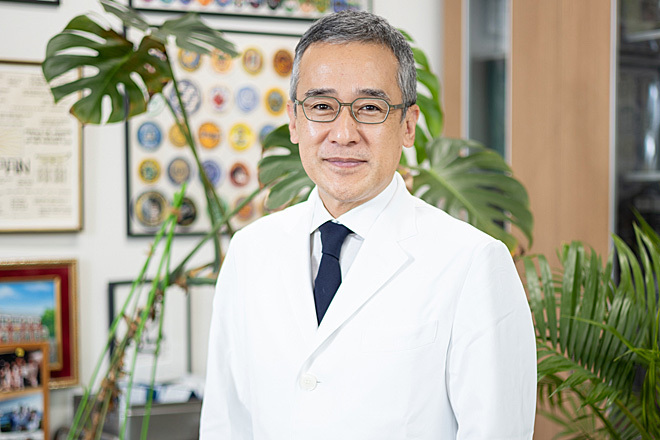
能登半島地震の被害を受けた石川県で、長崎大病院感染制御教育センター長の泉川公一教授が、避難所の感染症対策に当たっている。泉川氏はじほうの取材で、発災から1カ月半たち、各地の避難所で当初の過密状態が是正されつつあるが、一部では新型コロナのクラスターも確認されていると説明。「油断できない状態が続いている」とした。
泉川氏は、日本環境感染学会の災害時感染制御支援チーム(DICT)の責任者を務める。
DICTは、感染制御の実務経験者で編成する学会主体の専門家組織だ。特に避難所の集団感染リスクを減らすため、被災地の感染対策チーム(ICT)への支援や、必要な対策を講じるための情報収集などに当たる。東日本大震災(2011年)や熊本地震(16年)の経験を踏まえ、能登半島地震で本格的に組織化し、活動している。
今回、泉川氏は先遣隊として、1月3日午前に石川に入った。以降、複数回にわたって被災地で活動。現地の保健医療福祉調整本部、金沢医科大、避難所などで、情報収集や関係者との協議を続けてきた。DICTは今月19日まで常駐し、その後は、県内の医療関係者でつくる感染対策組織をサポートする予定だ。
●感染者数、「正確な把握」が課題
泉川氏は、避難所の最近の状況について、被災者を一時的に受け入れる「1.5次避難所」や「2次避難所」の整備が進んだこともあり、当初の過密な状況は改善が進んできたと説明した。
しかし、コロナのクラスターが発生した避難所もあるとして、今後も緩むことなく感染制御の対応を続けることが重要との認識を示した。いまだに、断水などで十分に感染対策できない地域もあるため、可能な範囲で対策を講じるよう呼びかけている。
それぞれの避難所での各感染症の感染者数の把握は、関連データベースのひも付けが十分ではなく難しいと説明した。より効果的な感染対策を取るためには、正確な感染者数や有症状者数の把握が、今後の課題だとした。
●感染対策物資、「平時から十分備蓄を」
足を運んだ避難所の多くでは、感染対策として手指消毒用のアルコールが備えられていたとし、「新型コロナの経験が生きている」と評価した。
ただ、発災直後には、次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒薬や、簡易トイレを含めた感染対策物資が行き届いていなかったと指摘。「行政が中心となって、平時から、感染対策物資の十分な備蓄を行っていることが大事ではないか」と提言した。








